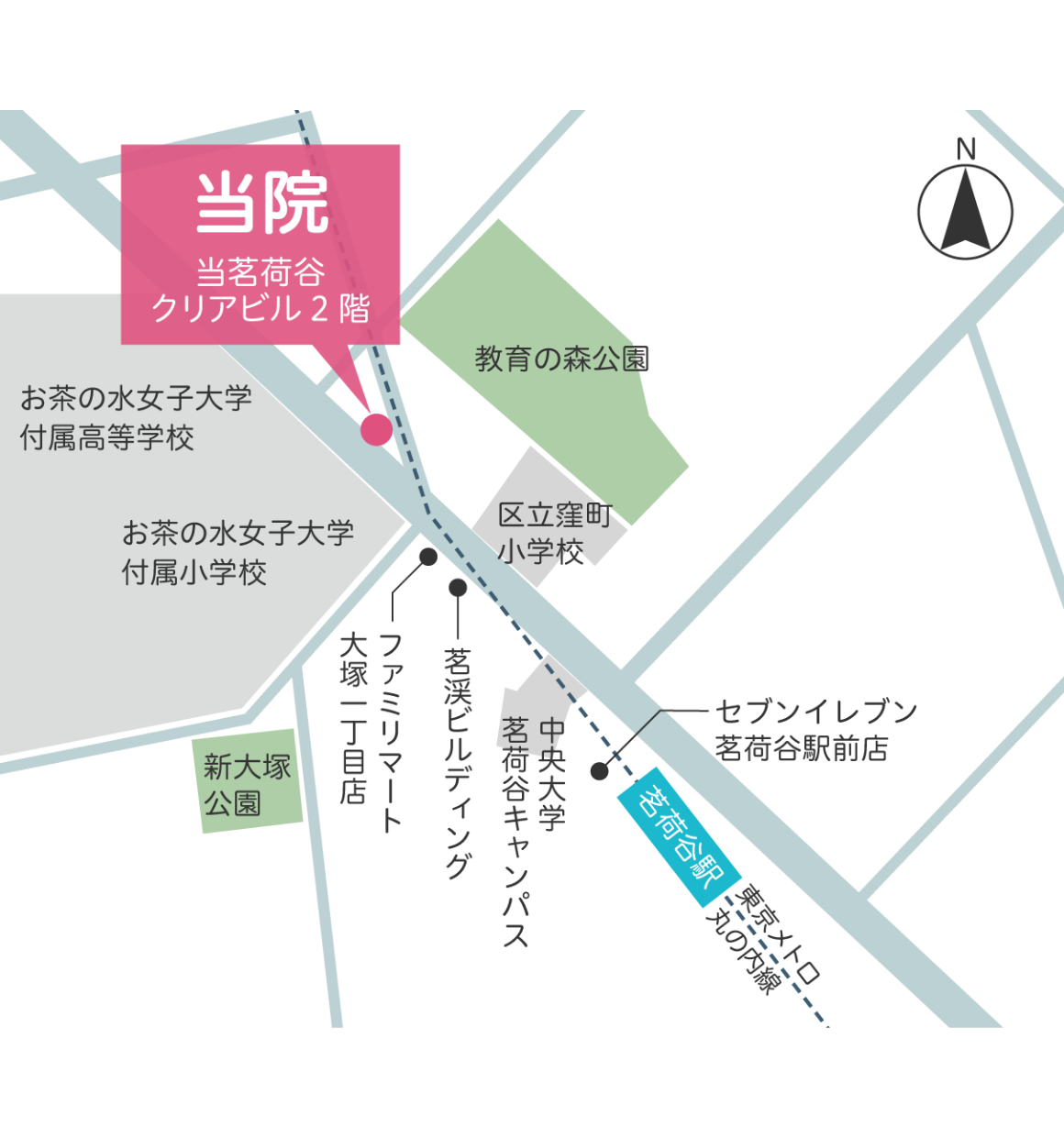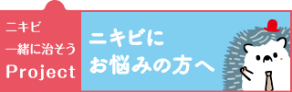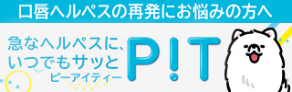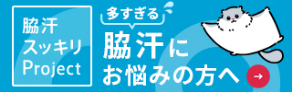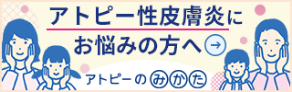水虫とは
足底や足指の間などの皮膚にカビ(真菌)の一種である白癬菌が感染し、それによって発症する皮膚疾患を一般的に水虫といいます。正式な疾患名は足白癬です。白癬菌は、手、体部、股部などの皮膚にも感染しますが、白癬菌が原因の皮膚疾患の半分以上は足白癬(水虫)の患者様です。
感染経路については、不特定多数の方との足ふきマットやスリッパの共用、公衆浴場やプール等の場所を裸足で歩き回るなどすることで感染するとされていますが、足の皮膚に白癬が付着しても感染するまでには24時間程度かかります。そのため、その間に足を洗い流すことができれば感染は防げるようになります。ただ足の裏に傷があるなどすれば、その半分の時間で感染に至ることもあります。
なお一口に水虫と言いましても、症状の現れ方によって3つのタイプに分けられます。ひとつは足の指の間に発生する水虫で趾間型です。なかでも第4趾と第5趾、いわゆる薬指と小指の間に発生することが多いです。高温多湿な時期に発生しやすく、患部は赤みや小さな水ぶくれ、ただれなどがみられ、乾燥すると皮がボロボロ剥けていきます。かゆみの症状もあります。また足の指の付け根、土踏まず、足側縁等の部分に小さな水疱が多発する小水疱型もあります。これは症状が進行するとかゆみも出ますが、水疱が破れるなどして乾燥すると鱗屑(皮がポロポロ剥ける)がみられるようになり、かゆみの症状も治まるようになります。同タイプも高温多湿な時期に起きやすいです。3つ目の角化型は、発生する確率としてはかなり少ない方です。足底(足裏)の角質層が全体的に肥厚化している状態で、かゆみ等の症状が出ることはありません。ただ乾燥している踵の部分に亀裂が入るなどすれば痛みが強くでるようになります。
このほか足白癬をきっかけとして、そのまま足の指の爪に白癬菌が感染してしまうことがあります。これを爪白癬といいます。この場合、爪は白や黄色に濁るなどして、さらに肥厚や変形等がみられるほか、脆弱化もしていきます。そのため、爪を切ろうとしたらボロボロ崩れてしまったというケースも少なくありません。ちなみに痛みやかゆみなどの症状はみられません。
検査について
当院では、患者様の訴えや症状から水虫が疑われる場合は、皮膚の一部を採取し、白癬菌の有無を調べるための顕微鏡検査を行い、診断をつけていきます。
治療について
検査の結果、治療が必要となれば、主に抗真菌薬の外用薬を患部に塗布していきます。ただし、角化型や爪白癬の患者様につきましては外用薬が浸透しにくいので、内服薬を服用していきます。